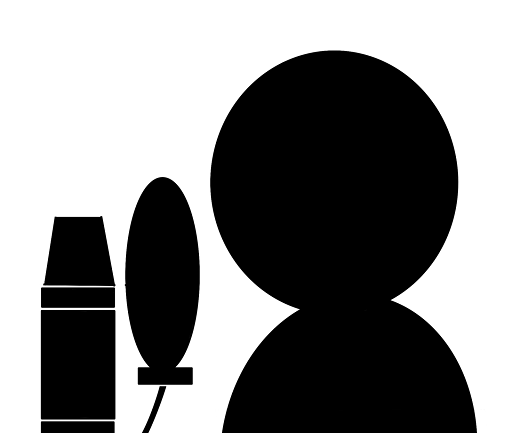番組に欠かせない、縁の下の力持ち!
今回は新人ADがつまづくポイントでもある、ナレーション原稿の作り方について解説したいと思います!
まずは、そもそもナレーションとはどういう意味があるのか、説明していきます。
ナレーションとは、声だけを使った表現で視聴者により分かりやすさを与え、番組に引き込ませてくれる仕事です。
1つ大きなポイントとしてあげられるのは声からテンションが伝わるということです。
ナレーション原稿を渡して読んでもらう時に「どういうニュアンスで読んでもらいたいのか」まで書いてあることはあまりありません。
ですが、その番組が元気いっぱいに届けたいのか、怖がらせたいホラーなのか、番組の色を足してもらうためには、初めにイメージも伝える必要があります。もっと手前でどのナレーターさんにお願いするかを考える段階でも、イメージに合う人を選ぶことも大切です。声のサンプルや他番組などを参考にナレーターさんを選ぶことが多いです。
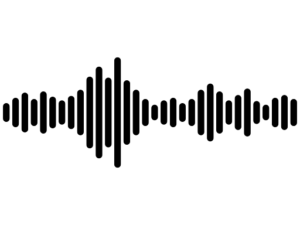
ナレーション原稿の作り方
まずナレーション原稿を作る時には、ディレクターがVTRに乗せたナレーションを起こした上で、書き出しと照らし合わせて確認する作業から始まります。
最近はディレクターが編集しているプレミアのプロジェクトから書き出すことができるようになっており、作業もだいぶ楽になるので、それをまずは解説していきます。
プロジェクトのナレーションのみを書き出す
ディレクターが書き出すプロジェクトの該当シーケンスを開き、ナレーションのテキストのみをひとつのバーに乗せ、それ以外を「⌘+A」で全て消します。そこから書き出しでXMLファイルを作成します。そのあとはネット上のサイトでテキストに変換してください。するとタイムと文言のみに変わったテキストが表示されます。それをワードファイルに貼り付けて作業します。
テキストの整理
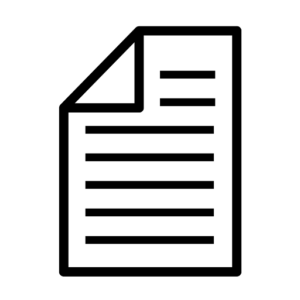
テキストになった原稿はプロジェクトのシーケンスタイムで表示されるため、読んでほしい正確なタイムではありません。一般的には1秒=30フレームで作業されます。(1分が60秒であるのと同じ理論です)1秒5秒29フレームで入っているナレーションについては1分6秒として切り上げて表記するのがいいため、このような細かい部分を微調整していく必要があります。
また、テキスト自体も分かりやすい表記にする必要があります。ナレーション原稿は四桁の数字で表記するのが一般的です。
例えばVTR開始直後の5秒で読んでほしいナレーションがある場合には0005、15分30秒であれば1530であるように、統一で表記されます。
⚠︎豆知識⚠︎
番組にもよりますが、書き出したもの自体は00:00:00などで表記されているため、ワードを使って00:の部分を消したいとします。
その場合にはワード右上の「文書内を検索」にある▽を押して「検索結果をサイドバーに表示する」を押します。
検索と置換の欄から削除したいもの(上記の場合には00:)を上のバーに入れ、すべて置換を押すとその文字が消えます。(00:が何もない状態に置き換わったということです)
これだけでも単純作業のひとつが簡単に終わるので覚えておくといいと思います。
VTRと照らし合わせる
ここまでの作業は書き出しがなくても、書き出している途中のプロジェクト上でできる作業です。
ですが、作業の間にこぼれてしまったナレーションがないか、重複しているものがないかは実際に書き出したVTRを見ないとわからないことが多いです。同じタイムに異なる文言がある場合などはディレクターに確認して、正しい原稿になるようにしましょう。
原稿を作る際に注意しないといけないのは、不明確な情報がクリアになっているかどうか確認することです。
ディレクターが確認仕切れていない数値などが@で入っていることがあります。そのほかにも出てきた人の名前の読み方などの情報があっているか、商品名などについては正しいものが入っているか確認することも必要です。
読んでいる人の気持ちを考える
チェックなどの段階で行う原稿の作成作業はここまでできればある程度大丈夫ですが、ナレーターさんに読んでもらう原稿についてはより細かい作業が必要になります。
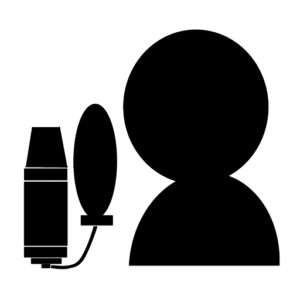
実際にナレーションを読む人は、編集作業に入っているスタッフのようにずっと前からVTRを見ているわけではないので、そのあとの展開を知っているわけではありません。
ナレーションを読む人は読み始めるタイムと文言しか原稿上で渡されていないと、わからない情報がまだまだたくさんあります。そのわからない部分をなるべく減らすために様々な要素を足していきます。
終わりのタイムを書く
一番多くすることとしては終わりのタイムを書くことが挙げられます。
読み始めのタイムを四桁で記載するのが一般的だとお伝えしましたが、終わりのタイムは二桁であることが多いです。どこまでに読めばいいかわからないと言ったのですが、相手もプロですので、二桁の終わりのタイムがあれば逆算して読んでくれます。それでもなお収まりきらないときには、ナレーターさんとディレクターが相談して、文言の修正を行うこともあります。
ONを入れる
ナレーションを読む直前、直後のON(=素材の中で演者が喋っている声)を入れてあげることで、「この会話が終わったらナレーションを読めばいいんだ」ということが伝わります。
逆に生かしたい会話があるときには、ナレーションの直後に入れておくと「ここまでに読めばいいんだ」と伝わります。複数人演者がいる場合には、タレントの名前を記載しておくとより丁寧だと思います。
カット変わりを記載する
映像で、次の映像に行ったときにナレーションを読んでほしいときには記載することもあります。
これはもちろんナレーターさんに読んでもらいたい文言ではないので、原稿を作るときに網かけするなどしておくといいと思います。
キューボタンを押す
ナレーションを読んでほしいタイミングで、ブース(アナウンスブース=アナブ と呼ばれます)の外にいるディレクターがキューボタンを押すとブース内のランプが光って、ナレーション読みの目安になります。ナレーターさんや番組にもよりますが、PRなどでADのうちから押すこともあるので、覚えておきましょう。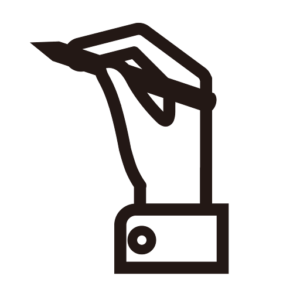
実際に読んでもらう前にもう一つ、ナレーターさんがわからないことが出てくるとすれば、固有名詞の読み方です。一般的な言葉には、我々よりも触れることが多いと思いますが、その番組で出てきた人や地名、商品名などは特殊な読み方をする場合もあります。
その場合には読み方だけでなく、切り方などのイントネーションを聞かれることがあります。しっかりと正しい情報を伝えられるようにあらかじめ確認をしておきましょう。また、固有名詞などについてはふりがなを振っておくとスムーズに進められます。
最終的に、原稿を紙に印刷して読んでもらうのですが、このとき、大き目のサイズの紙で用意することが多いです。
スタッフはA4でいいのに対して、B4やA3で印刷するのが一般的です。番組でどう準備したらいいかを確認した上で、編集所などのコピー機でどうしたらそのサイズに印刷できるのかを確認しておくといいでしょう。また、1部ずつまとめられるようにクリップを用意しておきましょう。
ナレーション録り中は変更した文言をまとめたり、全てのナレーションが読まれているかを確認して、ナレーション原稿の最終稿を作るようにしましょう。
まとめ
今回は、ナレーション原稿の作り方から、ナレーション録りの流れについて説明していきました。
ナレーションを録ったことがある新人スタッフはなかなかいないと思います。初めてだらけの作業だからこそ、入念な確認が大切です。様々な工夫によって、よりナレーターさんがわかりやすく、伝えやすくすることで、より良いVTRに近づくと思います。