前説をやるのは芸人だけじゃない!?
スタジオ収録の際、観覧客を入れた時に行われるのが「前説(まえせつ)」というものです。番組の収録前に観客へ諸注意を伝えたり、拍手やリアクションの練習をしたり、簡単なトークで会場を温めたりする、テレビ業界では欠かせない重要な仕事です。
一般的には芸人が担当するイメージが強いですが、実はADが前説を任されることもあります。特に若手ADにとっては、「現場を盛り上げるスキル」を身につける絶好のチャンスでもあります!「笑いを取るのは芸人の仕事」と思われがちですが、前説の目的は笑いを取ることだけではありません。
観客と番組の空気をつなぐこと、そして現場全体を明るくして本番がスムーズに始まるようにすることが一番の役割です。
ADが前説を担当するとき、「何を話したらいいのかわからない」「スベったらどうしよう」と不安になる人も多いかと思います。ここでは、実際の現場で使いやすく、すぐに応用できる前説のネタを紹介します。
どれもお笑い芸人ではなくても実践できる内容ですので、ぜひ自分なりにアレンジして活用してみてください!
前説で使えるネタ
季節ネタ

季節ネタは誰にでも共通の関心があるため、前説の導入にぴったりなトークテーマです。
たとえば、春なら「花粉がつらい時期になってきましたね」、夏なら「収録スタジオが一番涼しい場所かもしれませんね!」といった今の空気感を交えるのがおすすめです。
また、「春休み」「夏休み」「連休」といったキーワードは、年齢を問わず共感されやすく、「宿題は早めに終わらせる派でしたか? それともギリギリ派でしたか?」と観客に質問してみると、自然にリアクションが返ってきます。
秋は「食欲の秋!でも食べすぎると眠くなってしまう季節ですよね!」、冬なら「朝の集合時間が早いと寒すぎてスタッフより先にカメラが凍ります!」などジョークを交えながら、現場ならではの笑いを添えたり、また、「今日はこんな寒い中来てくださってありがとうございます!」など、観客への労いの一言を添えると、場が一気に和みます。
季節をきっかけにして、「最近○○しましたか?」と話を広げると、観客とのトークに自然につなげられます。
特技披露
特技披露は、前説の中でも人柄が伝わるネタかもしれません。
観客は、芸人ではなくADがマイクを持っているだけで「どんな人なんだろう?」と興味を持っています。そこで、自分の得意分野をちょっとだけ見せることで、親近感が生まれます。
たとえば、モノマネ・早口言葉・手品・リズム芸など、短くてテンポの良いものが好まれます。「くだらない」「しょうもない」くらいがちょうどよく、笑いのハードルを下げ、お客さんは安心して笑ってくれます。過去、ADがオカリナ演奏をして、スタジオの空気が一気に明るくなった例もあります。
もし複数人のMCやスタッフがいる場合は、“特技対決”形式にして、「どっちの早口言葉が早いか?」など、簡単な勝負にしてもいいかもしれません。
重要なのは、“うまさ”ではなく、“勢いとノリ”。
成功しても失敗しても笑い変えられるのが、前説の強みです。
ご当地ネタ
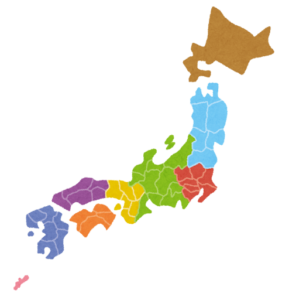
観覧客が集まる番組では、地域の話題を取り入れるのも効果的です。
「この地域では○○をこう呼ぶんです!」という方言クイズや、地元のあるあるを取り上げると、観客が自然に笑顔になります。
他の番組スタッフの出身地に触れて、「うちのディレクター、北海道出身なんですけど、“寒い”って言わずに“しばれる”って言うんですよ!」など実際の裏話を混ぜると親近感が生まれます。
さらに、スタジオにいるお客さんに、「今日はどちらから来られたんですか?」と問いかけ、遠くから来たお客さんがいたら、その地域のご当地グルメや珍しい方言を聞いてみるのも良いかもしれません。
ご当地ネタを話すときのポイントは、「知らない言葉を面白がる」よりも、「その地域の魅力を伝える」方向に振ることです。
地元愛を大切にしたトークにすることで、スタジオ全体が温かい雰囲気になります。
クイズ・なぞなぞ・心理テスト
クイズやなぞなぞ、心理テストは観客の参加意欲を高めることができるネタです。お客さんに対して、こちらがクイズやなぞなぞを出すことで、お客さんを巻き込むことができます。事前にイラストを描いたボードやスケッチブックを用意しておくと、視覚的にも楽しめるため、子どもから大人まで飽きずに聞いてもらえます。コツは、正解や結果を重視するよりも、リアクションを拾うことです。
観客が「え~!」「そうなの?」と声を出した瞬間に、その反応を褒めたりツッコんだりすると、自然と笑いが生まれます。
テンポよく進めることで、本番前のウォーミングアップとしても効果抜群です。
以心伝心ゲーム

「以心伝心ゲーム」は、シンプルで誰でもすぐ参加できる人気の前説ゲームです。
ルールは、ADと観客代表がペアになり、お題に対して同時に答え、回答が一致するかどうかの簡単なルールです。
たとえば、
「夏の食べ物といえば?」という質問に対して、二人が同時に「スイカ!」と言えたら成功です。
簡単なルールではありますが、ADと観客の距離が一気に縮まり、笑いが自然と生まれます。さらに応用として、「全員参加型バージョン」もおすすめです。
お題を出して、スタジオ全員で同じポーズを取れるか挑戦してみてください。
たとえば、
「バレーボールといえば?」というお題に対して、全員がアタックのポーズをしたら成功です。
人によって違うポーズをするのも面白く、自然な笑いに包まれます。
正解よりもバラバラな結果を楽しむのがこのゲームのポイントです。
自虐ネタ
ADとしてのリアルな失敗談や恋愛エピソードも観客との距離を一気に縮めます。
たとえば、
「“もっと急いで動け!”って言われたので全力疾走したら、カメラ三脚に突っ込んでしまって“落ち着いて動け!”って怒られました」や「この前、学生時代の元カノが観覧で収録に来てて、ディレクターに“お前、顔引きつってるぞ”って言われました。」というように少しヒヤッとする話も照れ笑いや話す声のトーンで明るい雰囲気にすることができます。

まとめ
前説は、ただ場をつなぐ時間ではなく、「スタジオ全体を一つにする大切な時間」です。芸人さんだけでなく、ADやスタッフが担当することで、より観客は番組の裏側を感じられる貴重な瞬間にもなります。大切なのは、完璧なトークよりも「楽しませたい」という気持ちです。季節ネタや特技披露、ご当地トークやゲームを通して、お客さんとの距離を縮め、笑顔と拍手で本番へとつないでいきましょう。
